Digilent の ZYBO(格安Zynqボード)が発売延期を繰り返しているようで、ワクワクしながら様子見しています。
実は別件でちょっとだけZynqを火入れ確認程度に触ったことがあるのですが、なかなかスジがいいなと感じています。
特質すべきは(XILINXの動向も含めて)
- CPUコアから起動とロジック書き込みを前提としていること
(それでいてJTAGからは従来のFPGAと同じに使える) - パーシャルリコンフィギュレーション技術
- 超安価な高位合成ツール
といったところです。
こうなってくると、たとえばアップルストアやGooglePlay からソフトを買うように FPGA回路がエアダウンロードされてくる時代が近づいているのを感じます。
その際、問題となるのが互換性の問題でしょう。
世代やメーカー、スピードグレードなどによりRTL回路は変わるので、当然ながら統一的な規格や中間言語のような記述、端末側での動的合成などが必要になります。
また、デバイスごとのスピードの問題もあるので、クロックの抽象化や低即時にパフォーマンスが落ちるのみで住む(故障やシステム破綻につながらない)外部とのI/Fとしての標準プロトコルも必要にあってくると思われます。
言うなればハードウェア用に新しいOSのようなものがこれから必要になってくると思います。
ソフトウェアのOSがかつてそうであったように、非常に面白い領域が誕生してくれるのではないかと期待しています。
ちなみにFPGAのような領域では、浮動小数点やその他SIMDなどの効き易い計算ジャンルはCPU(AVXとかNEONとか)やGPUに適わないと思っています。
一方でバイナリ系のデータを扱う領域においては極めて強力です。通信系の処理とか一部のバイナリ系画像処理とか、そういったジャンルで面白い用途(キラーアプリ)がもう少し身近に現れてくれると計算機のアーキテクチャももっともっと面白くなるのではと思います。
FPGAの老舗のXILINXがFPGA部に拘らずに、NEONなどを詰んだARMを混載してきたのは、今後を期待させてくれる事態だと思っています。


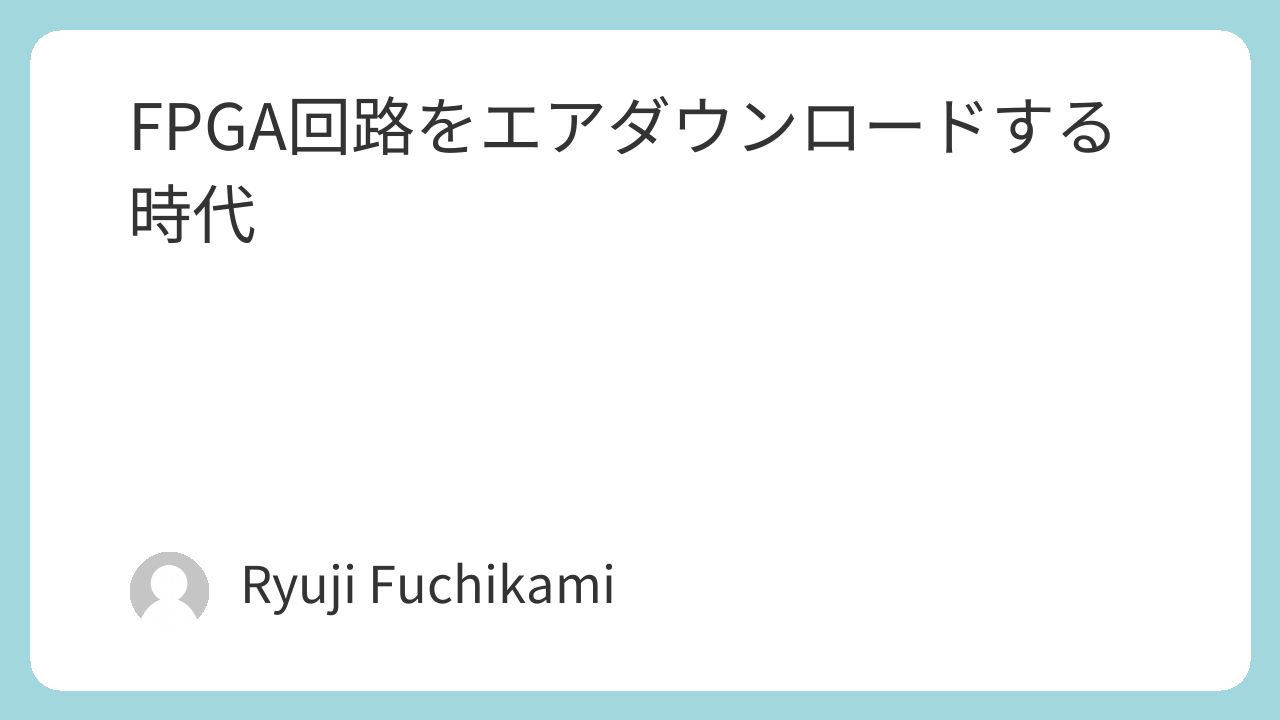



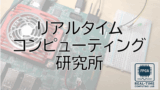
コメント