速報をあげた後、ゆっくり整理できていなかったので振り返っておきます。
<ペーストハンダ塗布について>
動画撮影した塗り方は初めてでかなりダメダメであった。
ニコニコに上げた動画で、ゴシゴシやったら滲まないかとのコメントを頂いたが、思いっきり滲んでしまって、アルコールで拭いてやり直した次第である。
スイッチサイエンスさんの動画などを参考に、一発で決めるのが吉。
しかしBGA用の穴は小さくて半田が入り込みにくいので最初にしっかり塗りこむことが重要そう。
<リフローについて>
最初こちらのレビューを参考にプリヒートのつもりで180℃指定したが、90秒ぐらいで解け始めてしまった。 今回有鉛半田を使ったせいかと思われる。
DigiKeyで1個単位で入手できるFPGAがPb-Freeしかなかったので、BGAは有鉛/無鉛混在という嫌な状況である。
そもそもBGAのボール自体ハンダなのでハンダペーストの塗布の重要性が掴めていないが、次はPb-Freeで統一したい。
<実装テスト>
自宅BGA実装でX線検査などはできない。
一方でFPGAであるから、I/Oに関してのテストは殆ど自在にできる。
特に、今回のように汎用端子に出しているケースにおいては、オープン状態でのショートチェックと、I/O同士を外部でつないだ導通チェックは可能である。
電源やGNDラインのチェックはできないが、一定数のI/Oエラー率を計測できれば、ある程度のレベルで信頼性の推定ができると思われる。
Soiiw 100*100mm 恒温ホットプレート PCB予熱ステーション PID制御 室温~400℃ 110V 350w基板製作 加熱エリア
<2012/09/29追記>
部品は3セット分発注していたので2セット目にトライして見た。
今回実はFPGAより厳しい部品としてDC/DCコンバータにLLPライクなパッケージであるLMZ10500を実装している。
結論から言うと、二回目はここがNGっぽい。保育園生の娘達の昼寝中を狙って超特急でトライして、半田のノリにヤバさを感じながらも眼をつぶってリフローしたのだが電源計測でショートっぽい抵抗値だ。
電源系は最悪外部から入れればいいというのと、DigiKeyで在庫ありの一番安いDC/DCモジュールだったというしょうもない理由での選定だったのだが、ある意味楽しい状況が生まれたといえる。
ということで、山善ホットプレートでのこいつのリワークを計画中である。
うまく行ったら報告します(報告が無かったら、察してくださいw)。


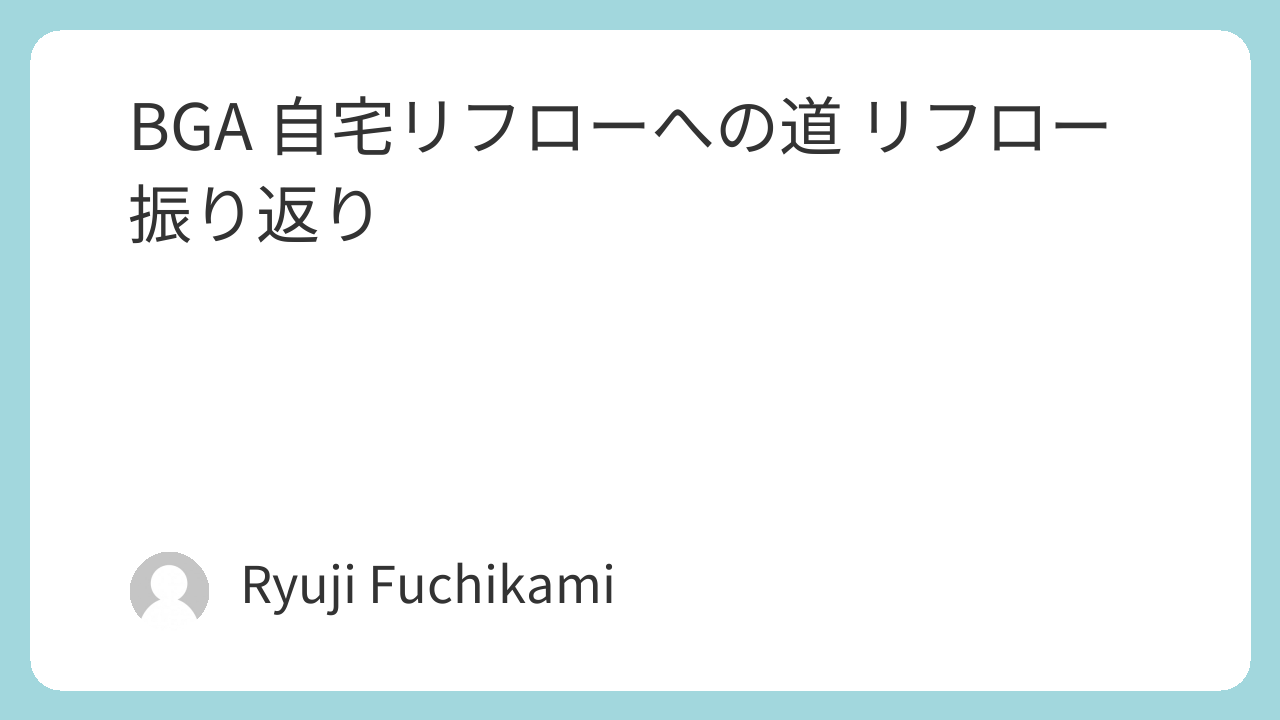

![[山善] ホットプレート 丸型 一人暮らし 1000W フッ素コーティング 簡単お手入れ 温度調節機能 保温機能 自...](https://m.media-amazon.com/images/I/41aAf7ZrfuL._SL500_.jpg)
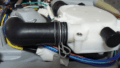
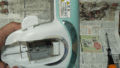
コメント