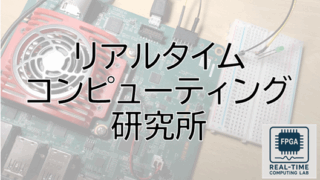 技術記事
技術記事 Ubuntu14.04-LTS
CentOSではLinaro上の開発にいろいろと不便もあって、Ubuntuで環境を再構築中以前の続きというか同じ内容なんですが、VivadoいれてPATH通して bash: /opt/Xilinx/SDK/2015.2/gnu/arm/li...
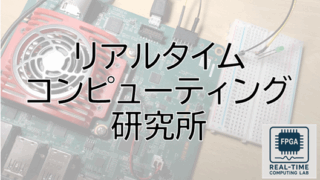 技術記事
技術記事 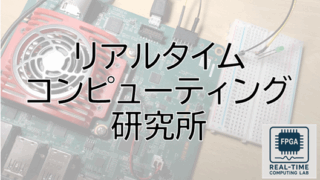 技術記事
技術記事 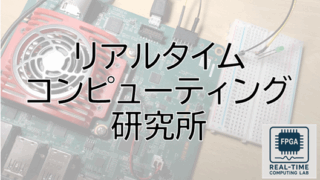 プログラミング
プログラミング 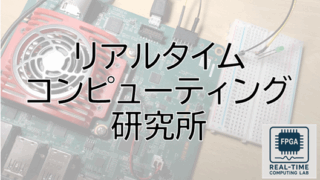 プログラミング
プログラミング 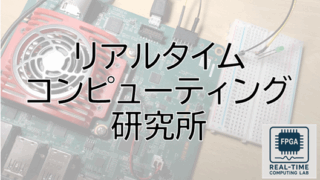 プログラミング
プログラミング 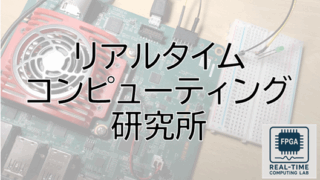 FPGA
FPGA 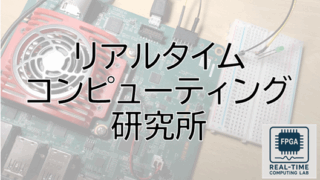 FPGA
FPGA 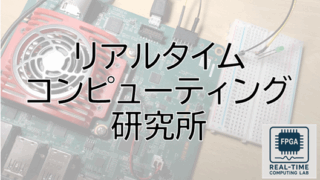 FPGA
FPGA 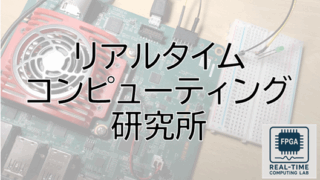 技術記事
技術記事 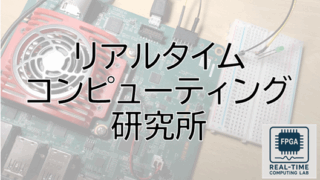 FPGA
FPGA